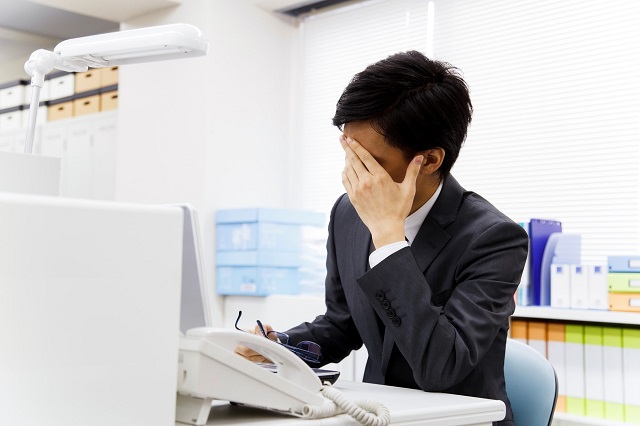コラムCOLUMN
- コラム
- BGMでの快適なオフィス環境作り
- 職場のアンガーマネジメント3選で社員のストレスを減らす方法
BGMでの快適なオフィス環境作り
職場のアンガーマネジメント3選で社員のストレスを減らす方法

社会人として仕事を進めていくうえで、コミュニケーションは非常に重視されます。職場でのコミュニケーションを円滑に進めるためには、自分の感情、特に「怒り」をコントロールし、冷静に対処することが求められます。これは、大人としてのマナーともいえるでしょう。今回は、怒りをコントロールする「アンガーマネジメント」の概要や、アンガーマネジメントを実践するための方法についてご紹介します。
アンガーマネジメントとは
アンガーマネジメントは「怒りを我慢するための技術」ではありません。むしろ、怒りが湧くメカニズムを知り、分析をしたうえで適切に対処するための技術です。
<怒りを我慢するのではなく、感情を管理して冷静に対処する技術>
日々のコミュニケーションの中では、思わぬ怒りを感じる場面もあるでしょう。特にビジネスシーンでは、怒りの感情をそのまま表現してしまうことは得策ではありません。怒りをそのまま表現することで、良好な人間関係を損ねたり、重要なビジネスチャンスを逃したりするリスクを伴います。
かといって、怒りの感情を抱えたまま仕事を進めてしまうと、大きなストレスを抱えることにつながります。このストレスは、仕事のパフォーマンスや人間関係にも悪影響を及ぼしかねません。そのため、仕事を円滑に進めるには怒りの感情をコントロールしつつ、健全な形で発散するスキルを身につけることが重要です。
<アンガーマネジメントを実践する6つのステップ>
アンガーマネジメントの6つのステップ
アンガーマネジメントは、一度にすべてを完璧に行う必要はありません。
以下の6つのステップを順番に実践することで、感情を上手に管理し、より良いコミュニケーションを築くことができます。[注1]
1. 気づき
アンガーマネジメントの最初のステップは「気づき」です。
「気づき」のステップでは、怒りが高まる前にその兆候を認識し、冷静さを保つ方法を学びます。「自分が怒りを感じている」と意識することで、衝動的な行動を防ぐことができます。
2. 知的理解
次に進むのが「知的理解」のステップです。このステップでは、怒りを表現することで起こるメリットとデメリットについて思考を巡らせます。自分の感情や行動が周囲に与える影響を分析することで、適切な行動を選択する基盤を築きます。
3. 感情的な理解
「感情的な理解」では、自分の特性を深く理解する理解する必要があります。「自分の怒りのパターンとは何か」「どのような状況で怒りが引き起こされるのか」を把握し、「自分の行動を変える必要性」に気づくことがこのステップの目的です。
4. 新しい行動パターンの学習
怒りに対処する新しい行動パターンを学びます。例えば、深呼吸やタイムアウト(その場を少し離れる)といった具体的なスキルを取り入れることが効果的です。
5. 新しい行動パターンの実践
学んだ行動パターンを日常生活の中で試してみます。特に、実際の怒りの感情が生じた場面での活用を意識することで、技術が徐々に身についていきます。事前にシミュレーションを行うことで、実践がスムーズに進むでしょう。
6. フォローアップ
アンガーマネジメントの最終的なステップは、怒りをマネジメントする考え方や行動を定着させる「フォローアップ」です。これらの一連の思考法や行動を繰り返し実践し、自分の中で習慣化することで、よりスムーズなアンガーマネジメントが可能です。[注1]
職場に取り入れやすいアンガーマネジメント3選

職場でも取り入れやすいアンガーマネジメントは3つあります。
日常的に忙しい職場環境では、ストレスや怒りをコントロールすることが難しい場面が多々あります。しかし、適切なアンガーマネジメントの方法を身につければ、職場でのコミュニケーションを円滑にし、良好な人間関係を築くことが可能です。ここでは、特に職場で取り入れやすいアンガーマネジメントの方法を3つご紹介します。
<怒りを感じたらまず6秒間数える>
1つ目の方法は怒りを感じた際に使えるマネジメント方法です。怒りを感じたときには、まず「6秒間数えること」を意識しましょう。
怒りをコントロールしにくくなる原因は、脳内で分泌されるアドレナリンの影響だとされています。アドレナリンが分泌されてから怒りが頂点に達するまでには、数秒間かかるといわれています。アドレナリンの分泌が収まるまでの間、怒りをこらえることでピークが去り、冷静さを取り戻すことができます。
たとえば、同僚の何気ない一言にイラっとした場合でも、6秒間を使って気持ちを落ち着けることで、その後の対応や言動に余裕が生まれます。怒りを抑えることで、建設的なコミュニケーションがしやすくなるでしょう。
<今怒りを表現することのメリットとデメリットを考える>
2つ目の方法は、今後の評価を考えることです。怒りをある程度抑えた後は、「今、この怒りを表現することがどのような結果を生むか」を考えてみましょう。このステップは、自己管理能力を高めるだけでなく、周囲とのコミュニケーションをより効果的にするポイントでもあります。
たとえば、怒りを表現するメリットとしては「気分が晴れる」「自分の感情を理解してもらえる」といった短期的な効果があります。一方で、デメリットとしては「職場での評価が下がる」「相手との関係が悪化する」などが挙げられます。これらを比較し、最善の対応を取ることで、冷静かつ理性的なコミュニケーションが可能になりビジネスシーンでの評価も上がりやすくなるでしょう。
< 怒りを表現する際は、冷静さと客観性を大切にする>
3つ目の方法として挙げられるのが、「完全にキレてしまわないこと」です。アンガーマネジメントを行い、怒りを適切にコントロールできたとしても、いざ意見を言うときに怒りが再燃してしまうケースもあるでしょう。
たとえば、部下や同僚に指摘をする場合、怒りに任せた言葉遣いではなく、状況や課題を具体的に伝えるように心がけましょう。このような伝え方をすることで、相手に対するリスペクトを示し、信頼関係の構築にもつながります。怒りの気持ちを言葉にすることは必要ですが、怒りで我を忘れてしまっては元も子もありません。そのため、自分の怒りを表現する際にはあくまで冷静に、客観的な視点を忘れないようにしましょう。
イライラ対策にはオフィスBGMも役立つ!BGMを取り入れる3つのメリット
アンガーマネジメントを行うだけでなく、従業員同士のコミュニケーションを円滑に進めるための工夫も重要です。特に、「リラックスできる空間」を作ることが健全な職場環境の鍵を握ります。その中で、オフィスBGMを導入することは、非常に有効な方法の一つです。音楽には心身をリラックスさせる効果があり、職場の雰囲気を向上させる大きな役割を果たします。[注2]
さらに、オフィスBGMを活用するメリットは、以下のような点が挙げられます。
<オフィスBGMが従業員のメンタルケアに果たす役割>
音楽が心身をリラックスさせる効果は、現代の職場環境におけるメンタルケアの一環としても注目されています。ストレス社会の中、多くの働く人がうつやストレスからくる自律神経の不調に悩まされる一方で、職場ではメンタルケアやチーム内のコミュニケーション向上が大きな課題となっています。これらの解決策の一つとして、「オフィスBGMの導入」が注目されています。心を落ち着かせる音楽を取り入れることで、従業員が心身ともにリラックスでき、職場全体のストレス軽減や良好なコミュニケーションの促進が期待されています。
メンタルケアへの貢献:音楽がもたらす癒しの効果
音楽には、心を和らげるリラクゼーション効果があることが知られています。そのため、オフィスBGMとしての音楽は働く環境に大きなメリットをもたらします。BGMが心地よいリズムを提供することで、自律神経のバランスを整え、心身の緊張を緩和する作用が期待できます。研究によると、リラクシングな音楽を聴くことで、ストレスホルモンの抑制とテストステロン分泌の促進が確認されています。このテストステロンは、性別に関わらず生きる意欲やストレス耐性に関与するホルモンです。分泌が増えることで、抑うつや不安の低減、さらには身体的疲労感の軽減にもつながります。特に午後の疲れがたまりやすい時間帯にBGMを流すことは、従業員の精神的安定とパフォーマンス向上に効果的です。
コミュニケーションを豊かに:職場環境における音楽の力
オフィスBGMが従業員間のコミュニケーションに与える影響については、興味深いデータがあります。研究では、オフィスにBGMを導入した期間、上司と部下などの垂直的な関係におけるコミュニケーション満足度が向上したことが明らかになっています。
音楽のリズムが職場に自然な親しみやすさを生み出し、緊張感を和らげることで、従業員が意見を交換しやすい環境が整います。その結果、職場全体の一体感や協力意識の向上につながります。
<気になる音や情報漏洩の防止につながるオフィスBGMのマスキング効果>
職場環境の改善や生産性向上において、オフィスBGMの「マスキング効果」は非常に注目されています。オフィスにはパソコンのキーボードの入力音や、電話対応の声など、想像以上に多くの雑音が存在します。こうした雑音は社員の集中力を削ぎ、ストレスを引き起こす要因になり得ます。
オフィスBGMを導入することで、音楽がこれらの雑音を覆い隠し、静かな環境を作り出すよりも、よりリラックスした状態で業務に集中できる効果が期待できます。また会議室や応接室にBGMを導入することで、情報漏えいのリスクを軽減するという、セキュリティ上のメリットも得られます。適切なオフィスBGMの活用により、働きやすい環境を構築するだけでなく、社員一人ひとりの心と成果にポジティブな影響を与えることができるのです。
仕事の質を高める音楽の力
オフィスBGMを適切に選び活用することで、従業員がストレスを感じにくく、仕事に集中できる空間が生まれます。また、リラックスできる環境はチーム内のコミュニケーションを促進し、職場全体の雰囲気を改善する効果も期待できます。
導入の際に考慮すべき具体的なポイントをいくつか挙げます:
- ・馴染みの薄いインストゥルメンタル楽曲を選ぶ
言語情報に気を取られることなく、作業に没頭しやすくなります。 - ・音量を適切に設定する
雑音をカバーしつつ、仕事の邪魔にならない音量に調整しましょう。 - ・シーンに応じた選曲を行う
作業内容や会議シーンに合ったBGMを選ぶことで、効果を最大化できます。
< 受付や窓口で流せば企業のイメージアップにつながる>
オフィスの受付や窓口は、企業の「顔」ともいえる重要な場所です。訪れるお客様が最初に接するこの空間で受ける印象は、企業全体のイメージを左右する大切な要素となります。このような場所にBGMを導入することで、来客に良い印象を与え、企業イメージを向上させることができます。研究によれば、空間に合ったBGMを流すことで、その場の雰囲気を好ましいものに変える効果があることが示されています。例えば、エレガントな雰囲気を目指す場合はクラシック音楽が高級感や清潔感を演出し、ナチュラルな空間ではリラックスできるカフェ風のBGMが居心地の良さを高めるといったように、音楽の選び方次第で空間の印象を自在にコントロールすることが可能です。
オフィスBGMは単なる装飾ではなく、来客の第一印象を良いものにし、企業のブランドイメージを向上させる重要なツールです。ぜひ、企業の顔である受付や窓口に適したBGMの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
BGMが受付や窓口にもたらす3つの効果
- ・第一印象をポジティブに変える
BGMには、訪問者が受ける第一印象をポジティブに変える力があります。研究では、適切なBGMを流すことによって、「冷たい」「高圧的」といったネガティブな印象を和らげ、「親しみやすい」「誠実」といったポジティブな感情を引き出す効果が確認されています。 - ・企業のブランドイメージを高める
受付で流すBGMは、企業のコンセプトやブランドメッセージを伝える効果的な手段です。例えば、洗練された印象を与えたい場合には「salon classic~洗練のオフィス~」、親しみやすさを強調したい場合には「朝のオフィス・ミュージック~カフェ~」などの音楽を選ぶことで、訪問者に、その企業らしさを感じてもらえます。 - ・リラックス効果で心地よい空間を提供
適切なBGMは、来訪者だけでなく受付担当者にもリラックス効果をもたらします。心地よい音楽が流れる空間は、自然な会話を引き出し、スムーズなコミュニケーションを実現します。このように、BGMは訪問者と企業の双方に良い影響を与える重要なツールです。
受付に最適なBGM選びのポイント
空間のコンセプトや目的に合わせてBGMを選ぶことが、効果を最大限に引き出す秘訣です。
例えば、エレガントな空間には「ライト・クラシック」、ナチュラルな空間には「カフェ・ミュージック」が最適です。BGMを取り入れることで訪問者に心地よい体験を提供し、企業の信頼感や好感度を高めることができます。このように、オフィスBGMは訪問者に与える印象だけでなく、企業全体のイメージ向上にも寄与します。音楽の力を活用する新たな取り組みは、ビジネスの成功を後押しする重要な要素になるかもしれません。特にオフィス環境の改善やコミュニケーションの活性化に取り組む企業にとって、BGMは見逃せない要素といえるでしょう。
アンガーマネジメントやオフィスBGMを活用した職場改善
アンガーマネジメントは単に怒りを抑えるのではなく、怒りの原因について考え冷静に行動を選択するためのものです。アンガーマネジメントを取り入れることで、仕事を進める際のストレスを軽減し、円滑なコミュニケーションが可能になります。結果として、周囲からの評価も上がりやすくなるでしょう。職場で実践するためには「怒りを感じてから6秒間数える。」「今怒りを表現することのメリットとデメリットを考える。」「怒りを表現する際は冷静さと客観性を大切にする。」といったことが挙げられます。さらに、職場全体でストレスを軽減するための取り組みとして、オフィスBGMを導入するのも効果的です。さまざまな方法で、社員が怒りをコントロールできるように対策していきましょう。
Sound Design for OFFICEで理想の職場づくり
「Sound Design for OFFICE」では、職場環境を改善するための戦略的なオフィスデザインを提案しています。
<職場に適したBGMの選び方>
特に注目されるのが、オフィスBGMの導入です。適切なBGMは、職場の雰囲気を和らげ、社員の集中力やリラックス効果を高めるといった利点があります。
以下のようなBGMチャネルを選択することで、快適で生産性の高い職場環境を実現できます。
BGMチャンネルおすすめコンテンツ
<理想的なオフィス環境を実現する戦略的な音楽デザイン>
オフィスBGMの導入だけでなく、従業員のメンタルケアや、職場内の円滑なコミュニケーションを促進するための多彩なソリューションをご用意しています。これらの取り組みを通じて、職場環境の改善と企業イメージの向上をサポートします。
公式サイトでは、今回の記事や関連コラムなど、役立つコンテンツを多数掲載しています。
職場環境改善に役立つヒントをぜひご覧ください。
コラム特集
「Sound Design for OFFICE」なら、音楽の力を活用して新しい職場改善の可能性を見つけられます。まずは気軽にお問い合わせいただき、職場環境の質を高める第一歩を踏み出しましょう。

オフィスにBGMという発想を。オフィスにBGMを流すだけでポジティブな効果がたくさん!
オフィスには「オフィス専用」のBGM、ぜひ試してみませんか?